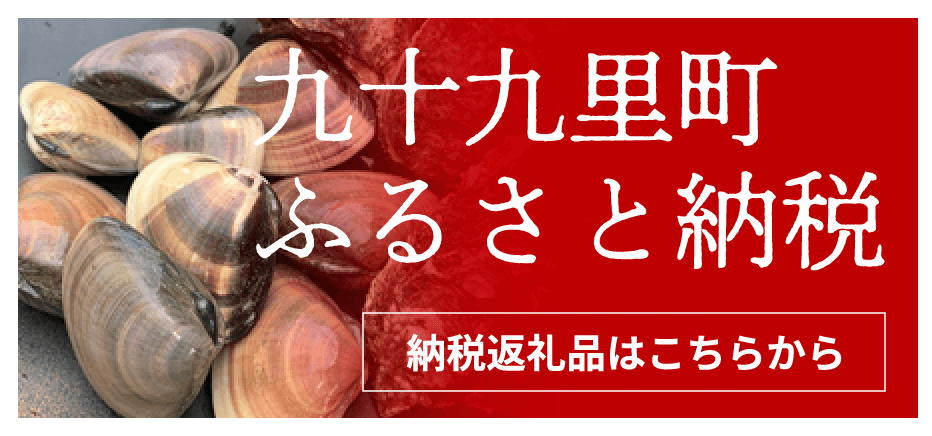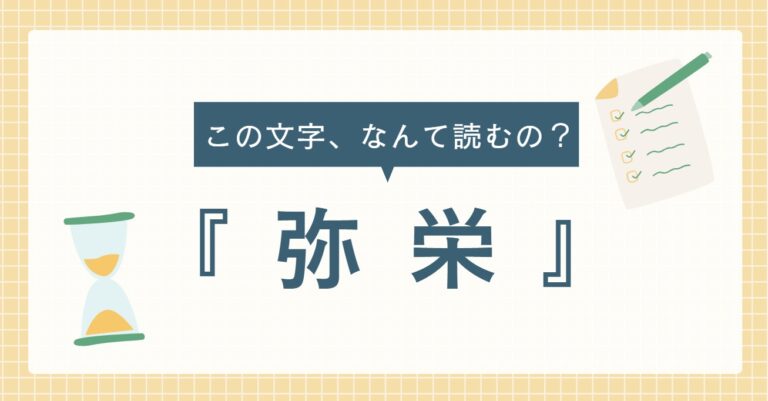お祝いの席で「弥栄(いやさか)!」と乾杯したことはありますか?「弥栄」は、「ますます栄える」という意味を持ち、日本の古くからの祝福の言葉です。現代でも、神社の奉納や式典、ビジネスの門出、お正月のご挨拶などで耳にすることがあり、縁起のいい言葉として古来より使われており、近年見直されてきております。この記事では、そんな「弥栄」の意味や語源に触れながら、縁起物としての食べ物「ハマグリ」の魅力を深掘りします。弥栄と縁起、そして美味しさと健康。それらをつなぐのが、実はこの“貝”なのです。
目次
1. 弥栄とは?その語源と使い方
「弥栄(いやさか)」とは、「弥(いや)」=ますます、「栄(さか)」=栄えるという意味を持つ言葉で、「末永く繁栄しますように」という祈りの言葉です。語源としては、『古事記』や『日本書紀』などにも記述が見られる古語で、「彌榮」や「弥盛」など、表記にもバリエーションがあります。現代でも「いやさか!」と乾杯の掛け声として使われることもあり、神社や伝統行事、ビジネスシーンの節目などでも使用されています。
2. 弥栄と乾杯の関係
日本酒での乾杯のときに、「弥栄!」という言葉が使われることがあります。これは単なる習慣ではなく、そこに“共に繁栄する”という強い願いが込められているからです。「弥栄」という言葉は、個人だけでなく、チーム、企業、地域、国家など“みんなで”栄えることを願う言葉。お正月や結婚式、会社の創業記念、ビジネス契約成立時など、人生の節目で古来から使われるのは、そこに深い意味と祈りが込められているからです。
3. 乾杯の由来と縁起の意味
「乾杯」という言葉は、中国の古典『漢書』に登場します。当時は、敵意がないことを示すために杯を乾かして飲み干す=乾杯という所作が生まれました。日本においては、乾杯は「良いことの始まり」として扱われることが多く、乾杯を交わすことで、その場を祝福し、未来の幸運を祈る意味を持つようになりました。そのため、乾杯の際に「弥栄!」と声を合わせることで、祝福の力はより強くなるのです。
4. 縁起を担ぐ食べ物としての「はまぐり」
蛤(はまぐり)は、古来より“縁起の良い食べ物”とされてきました。理由のひとつが、その特徴的な形状。ハマグリの貝殻は、対になってぴったりと合うようにできており、他の貝とは絶対に合わないことから、「夫婦円満」や「良縁」の象徴とされてきました。特にひな祭りでは、はまぐりのお吸い物を食べる風習があり、これも女の子の良縁と幸せを願ってのこと。さらに「貝が開く」ことから、「運が開く=開運」にもつながるとして、はまぐりはお祝いの席に欠かせない存在となったのです。
5. 「開く」食材=開運の象徴
「開く」という動作は、古来より“縁起が良い”とされてきました。たとえば、新年に“門松”を立てるのは「福の神を迎え入れるため」、つまり扉を開けること。また、宝箱が開く、花が開く、道が開けるなど、「開く」という言葉はすべて前向きな意味を持っています。その点、加熱により「開く」貝類は、まさに開運を象徴する食材。中でもハマグリは、形が美しく、味も濃厚、栄養も豊富。まさに、開運の象徴としてこれ以上ない存在です。
6. はまぐりの栄養価と健康への効果
縁起が良いだけでなく、はまぐりは栄養価にも非常に優れています。
主な栄養素
- タウリン:肝機能を高め、疲労回復や血圧の調整に効果的。
- 鉄分:貧血予防や免疫力アップに。
- ビタミン B12:神経系の働きをサポート。
- 亜鉛:亜鉛はたんぱく質の代謝を担っており、肌や粘膜を健やかに保ちます。
特にタウリンは、現代人の生活に欠かせない栄養素。飲み過ぎ、食べ過ぎ、ストレスが多い現代では、肝臓や血管への負担が増しています。そんなとき、タウリンを豊富に含むはまぐりを食べることで、身体を内側から整えることができるのです。
7. 茂丸のこだわりが生む、最高のはまぐり体験
茂丸株式会社では、以下の 3 つのこだわりをもって、皆さまに最高のはまぐりをお届けしています。
1. はまぐりへの飽くなき研究 o 季節ごとに異なるはまぐりの状態を研究し、最も美味しいタイミングを 見極めて出荷しています。
2. 時期に適した、厳選された産地直送 o 千葉・九十九里浜を中心に、全国の信頼できる漁場から選び抜いたはま ぐりのみをお届け。
3. 元プロ料理人の目線で発信する調理法 o 素材の味を活かした、おすすめの調理法などをブログで発信中。
(参考: ・ はまぐりの正しい砂抜き方法 ・ 2025 年 『土用の丑の日』 はいつ?)
8. まとめ:弥栄の想いを“はまぐり”とともに
「弥栄(いやさか)」という言葉には、人と人とが共に栄え、幸せになるという美しい願いが込められています。乾杯の際にその言葉を口にするとき、心の中で「縁起の良いものを食べて、みんなが健康でありますように」という願いを込めてみてください。そして、その縁起の良い食べ物として、ぜひ「はまぐり」を食卓に取り入れてください。美味しくて栄養豊富、しかも“開運”にまでつながる――。
はまぐりは、まさに「弥栄」を象徴する食材なのです。縁起を担ぐなら、味わいも担保された「本物」のはまぐりを。茂丸株式会社では、真心込めて最高の状態のはまぐりをお届けしております。
関連記事リンク