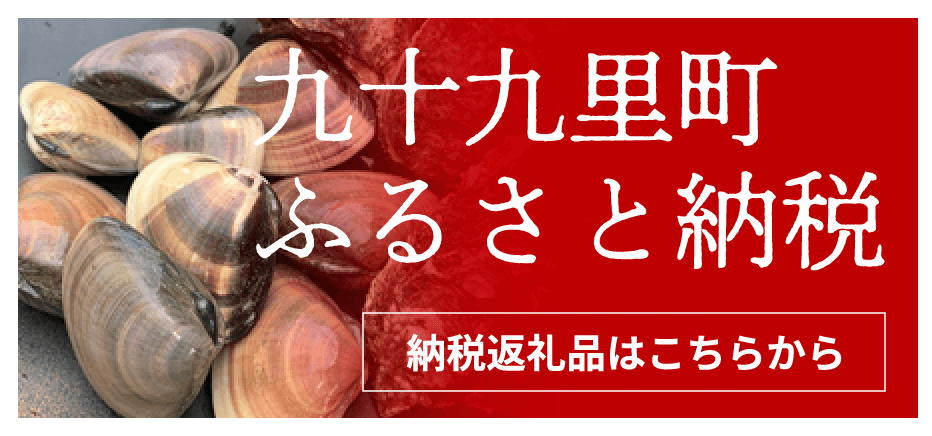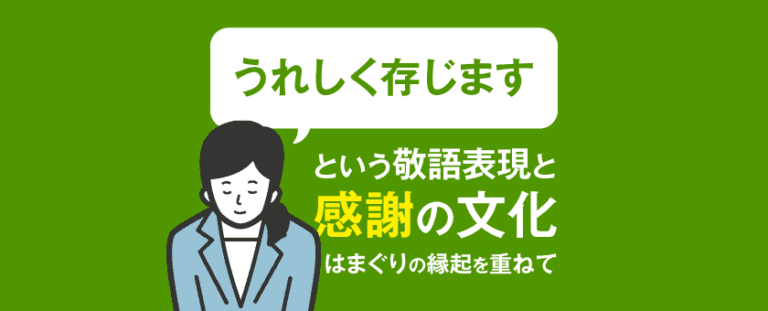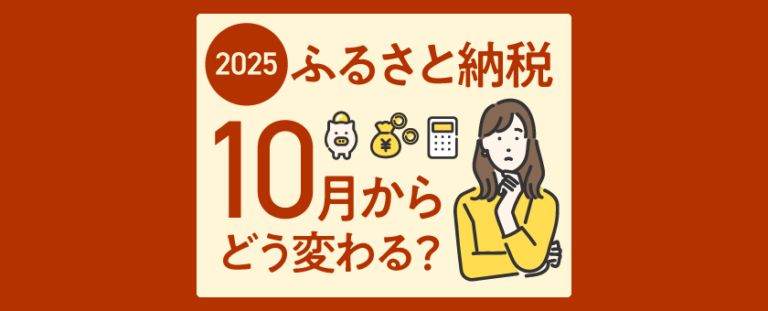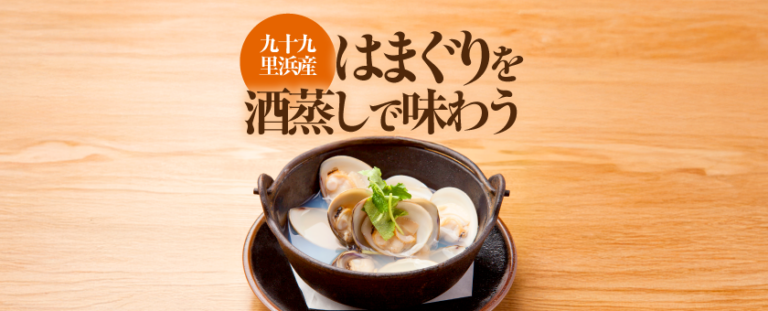目次
はまぐりの食べ方を極める──九十九里浜の漁師が語る“本当の旨さ”
潮の香りが漂う千葉・九十九里浜。
この記事では、「はまぐりの食べ方」をテーマに、焼き方や下処理、レシピ、九十九里浜の食文化まで、九十九里の海に関わってきた茂丸株式会社が誇る“本物の旨さ”をご紹介します。
はまぐりの魅力と食文化
はまぐり(蛤)は、古くから日本人の食卓に欠かせない“縁起の良い食材”です。
その理由は、貝殻がぴったり合うのが一対だけという特性。
他の貝とは絶対に合わないことから、「夫婦円満」「良縁」「再会」の象徴とされてきました。
また、ひな祭りでは女の子の幸せを願って、はまぐりのお吸い物を食べる風習があります。
さらに「貝が開く=運が開く」という意味から、“開運食材”としても知られています。
九十九里浜で育つ、旨味の濃いはまぐり
千葉県・九十九里浜は、はまぐり漁が盛んな地域として知られています。
遠浅の砂浜と潮の流れが絶妙で、肉厚で旨味の濃いはまぐりが育つのが特徴です。
茂丸株式会社ではこの地域の海から直送された“旬”のはまぐりを厳選し、最高の状態でお客様の元へお届けしています。
漁師直伝!焼きハマグリの極意
浜辺のBBQでも、家庭の網焼きでも、やはり一番人気は焼きハマグリ。
「焼き方」で味が決まると言っても過言ではありません。
🔹焼き方のコツ
- 網の上に殻の平たい方を下にして置く。
- 中火でじっくり焼き、口が少し開いたら醤油を数滴たらす。
- 完全に開いたら火を止め、身が縮む前に取り出す。
焼きすぎは禁物。はまぐりは加熱しすぎると固くなってしまいます。
髙山さん曰く、「貝が“ふわっ”と開いた瞬間が一番うまい」とのこと。
家でもできる!フライパン焼きのコツ
「BBQはできないけど、自宅で焼きたい」という方も多いはず。
そんな時はフライパン焼きが便利です。
フライパン焼きの手順
- はまぐりを軽く洗い、水分を切る。
- フライパンに並べ、蓋をして中火で加熱。
- 口が開いたら少量の酒を入れ、蒸し焼きにする。
- 香ばしい香りが立ったら、完成!
はまぐりの出汁がフライパンに広がり、まるで浜焼きのような風味に仕上がります。
はまぐりの下処理と砂抜き方法
調理前の下処理も、美味しさを左右する重要なポイントです。
新鮮なはまぐりでも、砂が残っている場合があります。
茂丸株式会社では、砂抜きの正しい方法を詳しく紹介しています。
👉 はまぐりの正しい下処理方法
基本のやり方は以下の通りです👇
- 塩水を作る(海水と同じ約3%の塩分)
- はまぐりを重ならないように並べ、冷暗所で2〜3時間放置
- 取り出したら殻同士をこすり洗いして完了
このひと手間で、雑味のない上品な味わいに変わります。
はまぐりの食べ方・レシピの楽しみ方
「焼き」以外にも、はまぐりには多彩な食べ方があります。
🔹お吸い物
定番中の定番。はまぐりの旨味が出汁に広がり、季節を問わず楽しめます。
🔹酒蒸し
シンプルながら、はまぐりの旨味を最大限に引き出す調理法。
お酒の香りが貝の甘みを引き立てます。
🔹しゃぶしゃぶ
九十九里の漁師たちが冬に好んで食べる方法。
薄い出汁にさっとくぐらせることで、身がふっくらと仕上がります。
🔹パスタや炊き込みご飯
はまぐりの出汁が染み込む料理との相性も抜群。
洋風にも和風にもアレンジ可能です。
茂丸株式会社の3つのこだわり
茂丸株式会社では、以下の3つの柱を大切にしています。
- はまぐりへのこだわりと飽くなき研究
季節や潮の流れによって変わるはまぐりの状態を研究し、
“今が一番おいしい”瞬間を見極めて出荷します。 - 時期に適した、厳選された産地直送
九十九里浜を中心に、全国の信頼できる漁場からのみ仕入れています。
自然環境と漁師の経験を活かした、品質第一の仕入れ方針です。 - 元プロ料理人の視点から最も美味しい食べ方を発信
茂丸代表・髙山茂勝さんが、プロの目線で調理法を監修。
ブログ内では調理法や保存法も発信中
まとめ:はまぐりで“家族の笑顔と縁起”を
はまぐりは、食材であると同時に“日本の心”でもあります。
その形には、絆・縁・幸福といった意味が込められているのです。
家族で囲む鍋、浜辺のBBQ、キャンプでの一人ご褒美──
どんなシーンでも、はまぐりは“幸せの味”を運んでくれます。
そして、その一つひとつを丁寧に届けているのが茂丸株式会社。
自然と人、食卓と心をつなぐ架け橋として、これからも“本物の味”をお届けします。