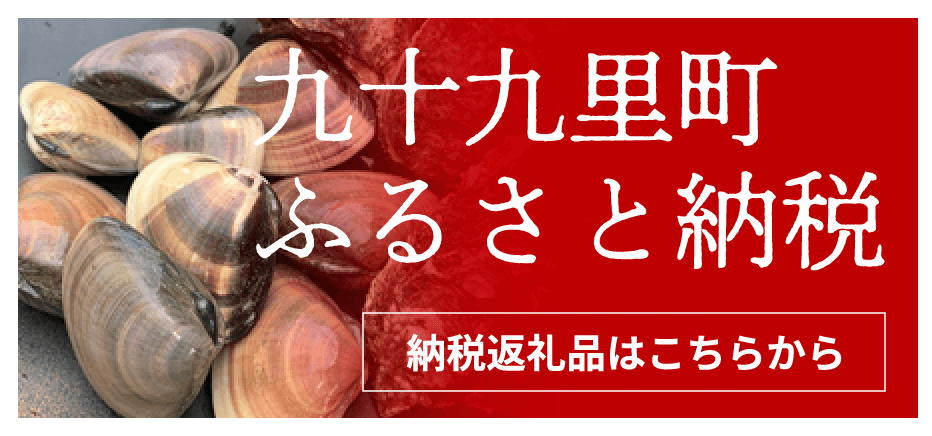「食育(しょくいく)」という言葉は、今や学校や行政の取り組みで耳にすることが増えました。しかし、日々の生活の中で「食育とは何か?」を深く理解し、実践できている方は意外と少ないかもしれません。食育とは、単なる栄養教育ではなく、「食を通じて人を良くする」ための幅広い学びと実践です。
本記事では、「食育とは 子ども」にも分かりやすく解説しつつ、九十九里浜で長年はまぐり漁を営む茂丸株式会社の髙山茂勝が、はまぐりを通して食育の大切さと楽しみ方をお伝えします。
目次
1. 食育とは?わかりやすく解説
食育とは、文字通り「食を通して人を育てること」。文部科学省は、食に関する知識や選択力、健全な食習慣を身につけることで心身の健康を育むことと定義しています。
これは大人にも子どもにも必要な、一生を通じた学びです。
特に「食育とは 子ども」にとって、家庭での食卓は最初の教室です。好き嫌いを克服する経験、旬の食材の美味しさを知る体験は、心の豊かさや健康の基盤となります。
2. 食育の取り組みと地域の食文化
全国各地で「食育 取り組み」が行われていますが、本当の意味での食育は地域の食文化と切り離せません。九十九里浜では、古くから海の恵みとともに暮らす文化があります。春のはまぐり、夏のイワシ、秋のサンマ、冬のカキなど、四季折々の魚介が食卓を彩ります。
茂丸株式会社の髙山茂勝は、「食育とは文化の継承でもある」と語ります。食べ物の背景を知ることは、命をいただく感謝の気持ちを育てる第一歩です。(参考: 初物を食べる意味・意義とは? )
3. はまぐりで学ぶ「旬」と「命の循環」
はまぐりは、春と秋が特に美味しいとされる二枚貝です。その理由は、産卵期や水温、餌の豊富さが関係します。旬の時期に採れるはまぐりは、旨みも栄養も格別。
この「旬」を知ることは、食育の重要な要素です。髙山は「旬の食材をいただくことは、自然のリズムに寄り添うこと」と話します。これにより、自然環境を守る意識も育まれます。
4. 家族で楽しむはまぐり料理
食育の魅力は「美味しく楽しい」ことです。例えば、子どもと一緒にはまぐりの酒蒸しを作ると、貝が開く瞬間に歓声が上がります。この体験は「命をいただく」という感覚を自然に学べる時間になります。
また、味噌汁や潮汁、バター焼きなど、調理法のバリエーションも豊富。こうした体験を重ねることで、子どもは料理への興味や感謝の心を育みます。(参考: 夏が旬!ながらみの美味しい食べ方! )
5. 茂丸のこだわりと食育
茂丸株式会社の 3 つのこだわりは、食育の実践そのものです。
1. はまぐりへの飽くなき研究 – 季節ごとの味や大きさを研究し、最も美味しいタイミングでお届け。
2. 厳選した産地直送 – 信頼できる漁場から直送、鮮度と品質を徹底管理。
3. 元プロ料理人による発信 – 調理法やレシピを通じて、美味しい食べ方を提案。
これらは「食べる人の健康と笑顔」を第一に考える姿勢です。
6. まとめ:はまぐりから始める家庭の食育
「食育とはわかりやすく」言えば、日々の食事を通じて健康と心を育むこと。家庭で旬の食材を楽しむことから、地域の食文化を学び、命の尊さを知ることまで含まれます。
九十九里浜の海の恵み、特にはまぐりは、その入口として最適です。栄養価が高く、家族で囲む鍋や酒蒸し、キャンプでの浜焼きなど、楽しみながら学べます。
茂丸株式会社では、真心込めて最高のはまぐりをお届けしています。ぜひ家庭の食育に、旬のはまぐりを取り入れてみませんか?